《51》 縦割りでできている困った社会
- 樋口彩夏
- 2014年2月19日
- 読了時間: 5分
前回、バリアフリーな設備がなくても、心のバリアフリーで超えられることもある、と書きました。
たしかに超えられるものはあるけれど、やはり、バリアフリーな設備も重要です。
今回は、「点から線のバリアフリーへ」をテーマに話を進めていきます。
2000年11月施行の交通バリアフリー法と、2006年12月に施行されたバリアフリー新法。
その効果もあってか、駅や空港、商業施設など各施設のバリアフリー設備は、年々増えているように思います。
その一方で、エレベーターが付いていないことで、車いすの人が利用できない駅がまだ存在しているのも事実です。
しかし、整備をするには、お金や構造上の問題もあるので、すぐにどうこうできない事情があるのでしょう。
各施設のバリアフリーは、このまま進んでいくと思うので、それも大切だ!とだけ、触れるにとどめます。
さて、電車・バス・飛行機などの交通インフラを使うのは、どういう時でしょうか?
それが趣味の場合を除いた多くの場合、どこかへ向かうための移動手段だと思います。
駅や空港の先には、目的地がある。
利用する人にとっては、そこへ着くことで、移動が完了するのです。
駅などの交通機関と目的地である商業施設などのバリアフリーが整いつつある今。
その間をつなぐ過程のバリアフリーが、忘れ去られている気がします。
たとえば、道路や歩道。
雨水などの排水のために設けられた勾配は、車いすで通るには難所のひとつでもあります。
必要なものとはいえ、傾斜が急なところもたくさん。
さがっている車道側へ軌道が逸れていくので、片方ばかり漕がなくてはなりません。
歩いていては気にならない傾きでも、車いすに乗っていると顕著に感じられるのです。
車道と歩道の境目にある段差も然り。
ウィリーという、前輪を浮かしながら進むテクニックが必要になってきます。
バスやタクシーはどうでしょうか?
バスの出入口には、2、3段の階段があります。
それを解消するため、階段下にスロープが収納されたものや、低床・ノンステップバスなども増えてきました。
でも、それは、都心に限られているのが現状です。
多くの地方では、まだまだ、車いすでも利用できる移動手段とは、なり得ていません。
以前、こんなことがありました。
スロープ付きのバスに乗ろうとした時のことです。
使用頻度が少ないからか、運転手さんはスロープの出し方が分かりませんでした。
私が説明をすることができたので、その場は問題なく乗れたけれど、こんなことがあってはいけないはずです。
ある日の運転手さんは、使い方はご存知だったようですが、スロープを引き出すための金具が錆び付いていて、使うことができませんでした。
これでは、宝の持ち腐れ。
設備があったとしても、ないも同然です。
バリアフリーな工夫がないところは導入を検討し、あるところは、きちんと使える状態を維持する必要があります。
駅だけが使えるようになっても、その先へ行けなければ意味がありません。
人の生活を考えると、それは容易に想像できるのではないでしょうか。
駅や目的地など、点のバリアフリーだけでは、実生活において使いものにならないのです。
点と点をつなぐ導線もふくめた、線のバリアフリーが必要です。
施設ごとに考えるだけでは不十分で、まちづくりとして全体的に考えるべきでしょう。
これは、建物の造りのみならず、情報の在り方にも同じことが言えます。
たとえば、鉄道の場合。
大きな都市になるほど、ひとつの路線ではなく、幾度かの乗り換えを経て目的地へ向かうことになると思います。
そのとき、乗り換えをする各駅が、車いすで利用できるかを確認しなければなりません。
最近では、ウェブサイトのどこを見ればよいのか、どのサイトが効率的に調べられるか等、要領を得てきました。
でも、鉄道会社が違うと、あっちを見て、こっちを見て、そっちを見て…と、とても忙しない作業になるのです。
サイトを行ったり来たりしているうちに、あれ?なに線のなに駅を調べようとしていたんだっけ!? なんてことも、しばしば。
もう、電話で聞いちゃおう!
当該駅・社のエレベーター事情を伺ったついで、あわよくば同駅構内にある他社の情報も…と尋ねてみたことがあります。
駅員さんの返答は、「他社の事情は分かりかねます」の一言でした。
その会社の駅については教えてくれるけれど、乗り換え先のことまでは範疇にないのです。
当然のことと言えば、それまでですが、はじめての駅を利用する度にくり返される、この作業からくるストレスは、相当なものです。
インターネットにしても、電話にしても、あちらこちらへ尋ねなくてはならないのが現状でした。
これでパソコンが使えない状況なら、バリアフリー情報を得ることだけを見れば、もはや鎖国に値するでしょう。
巷には、駅にあるエレベーターなどの情報を載せた、バリアフリーマップなるものが存在します。
それは、JRだけ、私鉄だけ、地下鉄だけ…という具合に、鉄道会社ごとの限局的なものに過ぎません。
でも、利用する私たちからすれば、鉄道会社に関係なく、おなじ移動手段なのです。
電車にも乗れば地下鉄にも乗るように、実際の生活には、縦割りで動いている会社の都合なんて、関係ありません。
スムーズな乗り換えができてこそ、鉄道網のもつ力が発揮されるというものです。
会社のへだたりを超えた、横断的なバリアフリーマップを求めます。
設備も情報も、それぞれが繫がってこそ、意味のあるものになるのではないでしょうか。
「点のバリアフリーから線のバリアフリーへ」
ただバリアフリーにすればいいのではなく、生活に則したバリアフリーが必要なのだと思います。
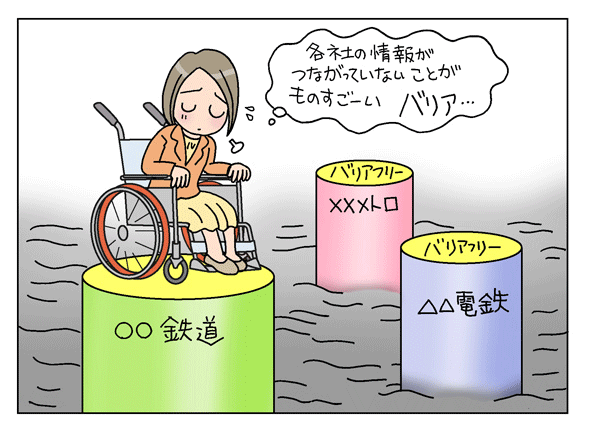
イラスト:ふくいのりこ




コメント